業界人インタビュー
【FRONTIER】「連携で切り拓く、映画の未来」ニューシネマワークショップ代表 高田道代さん×宣伝プロデューサー 奥村裕則さん スペシャル対談~後編~

ニューシネマワークショップ代表 高田道代さん
×宣伝プロデューサー 奥村裕則さん
スペシャル対談【後編】
映画業界の最前線で活躍する人々にインタビューする特別企画「FRONTIER 最前線」。
今年で29年目を迎える、映画学校・ニューシネマワークショップ(以下、NCW)。映画の宣伝も学べる学校として、広く映画業界への入口となってきた。2016年4月より、映画やエンターテインメント作品のデジタルプロモーションを手がけるフラッグが運営を担い、今年4月から、デジタルマーケティングを一層強化したカリキュラムに刷新した。
フラッグの執行役員で現NCW代表の高田道代さんと、マーケティングエージェンシーのサーティースリーで宣伝プロデューサーを務め、NCWの講師も務める奥村裕則さんの対談インタビュー後編では、映画人口の減少が進む中で、映画業界の課題も含め、SNS時代における映画宣伝のあり方を語っていただいた。
【前編】「学びが即戦力に変わる場所」NCW代表 高田道代さん×宣伝プロデューサー 奥村裕則さん スペシャル対談
炎上で変わったSNSへの意識
KIQ: 映画宣伝において、SNSへの意識はどの辺りから変わったのでしょうか?
高田: どこのタイミングって言われたら難しいですけど、炎上が大きな問題として捉えられるようになってから意識が変わってきたことは多いですよね。昔は、コンプライアンスって言葉もなかったですけど、そういう社会的な概念が生まれてくると、各企業も当然そこに倣って色々と整備しリスク管理していくので、宣伝としてもあらゆる立場の人たちへの配慮を熟慮するというのが起きていったと思います。
KIQ: 今は、炎上っていうのはどの程度意識されてるんですか。
高田: SNSは日々みなさんが日常で使うツールなので、基本的なことでいうと今日が何の日かっていうところがまずは大事で。終戦記念日だったり、地震や災害のニュースがあった日に文脈を間違えた投稿をしてしまうと、すべて紐づいて炎上していったりするので、タイミング的にそぐわなくなったものは見送ったり、配給にご相談したりします。今日という日がどういう日なのか、いま世の中で何が起きているのか、SNS担当は常に意識して、ニュースやトレンドをよく見るようにしています。フラッグでは大きな災害につながる警報が出たりすると、SNSメンバー全100人ぐらいが入っているSlackのチャンネルで共有して、意図しない投稿事故が起きないようにエスカレーションをしています。それがSNSベースだと結構多かったりするんですけど、宣伝計画を立てるときはどうですか?
奥村: 仰るように、やっぱり事件や事故、どうしても自分たちの計り知れないところで起きてしまうものに関しては、それと自分たちが扱っているものが何かリンクしてないかどうかっていうところのチェックはしますよね。例えば、街中で無差別に人を殺傷する殺人鬼のホラー映画を宣伝しているときに、世間で殺傷事件が起きてしまった場合は、やっぱり表だって告知していくことは非常に難しくなっていってしまうので、そういうものに関してはかなり敏感にはなります。リスクは常に考えますけど、でも自分たちがどんなに気をつけていても、何かが起きてしまうときっていうのはどうしてもあるなとは思ってますけどね。
高田: そうですね。少なくとも炎上を狙いに行くっていうことはしないですね。
KIQ: そのあたりをあまりよくわかっていないのでは?と思うようなものもときどき見かけますよね。
高田: 確かに「わかってない感」を感じる宣伝もあると思うんですけど、作品をヒットさせるために真剣にやってらっしゃると思うんですよ…たぶん狙ってはないと思うんですよね。
奥村: たまにちょっともう狙ってるんじゃ…?と思うときもありますが(笑)、本当にまずい内容のものとそうじゃないものがラインとしてあるような気はします。
映画宣伝は掛け合わせで勝負する時代
 左・高田道代さん 右・奥村裕則さん
左・高田道代さん 右・奥村裕則さん
KIQ: 新聞やテレビを通して展開させる旧来的な方法と、デジタルメディアを活用する方法とで宣伝効果は変わってきましたか?
高田: 若年層の人たちはテレビを見てないとか言われがちなんですけど、とはいえ、TikTokでバズるものがテレビの放送と連動していたりはするので、やっぱり絶対無視はできないですよね。なので、あまり宣伝で切り分けるというよりは、オフライン、オンラインでどれだけシナジー効果を出していけるかということの方が大事なのかなと考えてるんですけど、奥村さんどうですか?
奥村: その通りだと思います。単体として宣伝の効果が薄くなってきているメディアは確かにあると思うので、高田さんが仰ったように、掛け合わせてどう宣伝していくかですよね。やっぱり総合的に色々なところに作品のタッチポイントを作っていかないと、認知度が上がらなかったりとか、宣伝の機会損失みたいなところはあると思います。
KIQ: テレビとTikTokが連動しているとかってわかるのものなんですか?
高田: TikTokチームの方と話したときに、テレビとTikTokの相性はすごくよくて、TikTokで何かバズらせたいときは、テレビでイベント露出があるとか、全体的に他のメディア露出があるタイミングを狙った方がいいと伺って、そういった相乗効果を狙っていくのは重要だと思っています。TikTokだけでバズらせるっていうことよりも、じゃあそれを起点にどう広げていくのか、どうテレビで露出する方向に持っていくのか、色々なことを考えないといけなくて。昔はテレビはテレビ、SNSはSNSで、それぞれの連動まで考えていない感じだったんですけど、今は垣根なくやらないと、そもそも宣伝が成功しないっていう時代かなとは思ってはいます。
KIQ: 今も「紙・電波」「ウェブ」と分かれて宣伝されることが多いですよね。
高田: 同じパブリシティでもオフラインとオンラインでは戦略やそれにともなう企画、アプローチ方法も全然違うんですけど、それぞれの施策が点になってはいけないとは思っていて。さらにSNSと掛け合わせるっていうことを考えたときに、オンラインもオフラインも組み合わせて宣伝の波を作っていく必要があるので、宣伝全体では垣根は作らない方がいいかなと思います。ただ担当を全部ひとりがやるのは無理なのと、それぞれの職種の専門性もあるので、どう連携するか、スタッフ含めて一丸となれるかはキーポイントだとは思いますね。それを統括するのが宣伝プロデューサーですよね。
奥村: そうですね、やらないといけないですね。やっぱり作品やターゲットにもよってくるところはあるんですけど、テレビで見て、タイトルや設定を知って面白そうと思っても、中身のところまでは深くわからない。例えば、今は新聞もデジタル上でも読めるので、そこで評論を読んでもらえれば、中身のことをより知って、時代背景や社会性を理解した上で、その作品をさらに見たいと思ってもらえる。新聞に載ることでその作品が評論するにふさわしいという意味合いが生まれたりもする。
ただ、評論する人たちが減りつつあって、その力量や知識もなかなか受け継いでいけないことは危惧していて。今はSNSのインフルエンサーが出てきていて、彼らは彼らでちゃんと映画を伝える役割をもちろんやってもらってるとは思うんですけど、やっぱり評論家さんとはちょっと軸が違うから、そこが少しこれから足りなくなってしまうようにも感じます。
連携で切り拓く映画業界の未来
KIQ: 様々な媒体が連携していくことが一層重要になっていく中で、映画業界をこれからどのようにしていきたいと思われますか。
高田: フラッグは、松竹・東映と昨年に資本業務提携をして三社で「シネマDXプロジェクト」を立ち上げたんです。それぞれ劇場を持ってらっしゃるので、その劇場の顧客データを活用してより的確なターゲティングができるような広告商材の開発を現在進めています。あと、顧客データをもとに、実際に劇場に来ている人がどこのタッチポイントでその映画を知って、意欲を持って、最終的に劇場まで観に来られたのか、行動遷移を追う分析も行っていきます。顧客データ分析を基にした宣伝戦略を立てていくというのは他の業界では当たり前にやられていることですが、映画業界は配給と劇場が分かれてしまっているが故に、その顧客データを配給側が持てず十分なデータマーケティングが行えない現状があり、業界の課題になっています。フラッグは長らく映画業界のデジタルマーケティングに貢献してきた自負はあるので、マーケティングのDX化をやっていかなきゃいけないという使命感を持っています。
奥村: SNSも含めて、趣味嗜好が細分化されすぎているじゃないですか、今のユーザーたちって。その中で映画の時間を作るっていうことが非常に難しくなってきてますよね。
高田: 可処分時間ですよね。
奥村: いかにその映画自体の魅力を伝えるかというところもこの業界としては重要になってくる。なので、映画館で没入する体験がプレミアムなものだったりとか、その人にとって影響力のあるものだっていう付加価値をつけられたらいいですよね。作品単体でヒットを目指して、それを連動させながら次の作品へとつなげていくことも重要ではあるんですけど、この業界に求められる全体の使命としては、やっぱりユーザーたちの映画館に対する文化の底上げみたいなことも図っていくために何かしらやらないといけないと思います。
高田: 奥村さんのおっしゃっていることは私もすごく同感で。私たちはひとつひとつの作品をヒットさせるための宣伝を基本的にやっているんですけど、それが最終的に劇場で映画を観てもらう体験につながりはするものの、当然ながら宣伝だけで映画業界は完結するわけじゃなくて。映画が作られたあとに配給があり、宣伝があり、興行があることで、一般の人が映画を観られるという一連の流れがあります。劇場と宣伝がお客様に対して新しい劇場体験を作った方がいいんじゃないかというのはずっと思っていて、先ほどお話ししたシネマDXプロジェクトはその劇場との連動も視野に入れたプロジェクトとして動いています。
奥村: 全体がどう見えているか、これはたぶん本当にちゃんとひとりひとりが意識を持たないと難しい部分ではありますよね。
高田: そうですよね、それにプラスして、配給、興行、宣伝も一緒に業界に対してアクションを起こして、映画人口を増やしていけるようにしたいですね。
【Information】
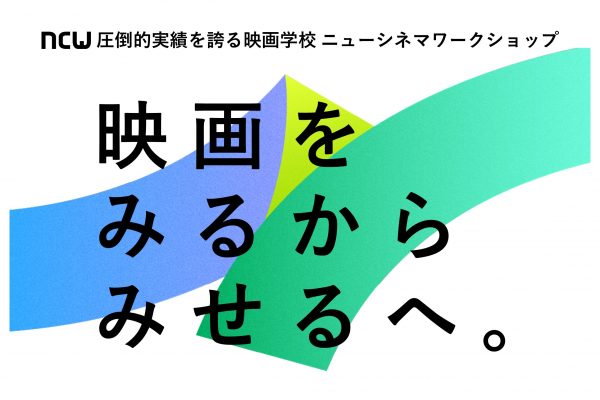
ニューシネマワークショップ
https://www.ncws.co.jp/
2025年に29年目を迎えるニューシネマワークショップは、映画を「つくる人」と「みせる人」を、どこよりも早く確実に養成する映画学校。
[つくる]コースでは、実習を中心に本格的な映画づくりのノウハウを習得することができ、『愛がなんだ』の今泉力哉監督や「silent」の脚本家・生方美久さんなど、映画やドラマの第一線で活躍しているクリエイターを多数輩出。
[みせる]コースでは、映画業界への就職を目指している人が“映画をみせる仕事”を学ぶことができ、これまでに600人以上の卒業生が映画配給会社や宣伝会社を中心に、興行や映画祭、メディアなどの様々な分野に就職し、多方面から日本の映画業界を支えている。
各コースは全て半年間で修了し、[ベーシック]と[アドバンス]の2クラスを受講しても1年間で自分の目指すところに到達できる。また、どのコースも週1日または2日のため、忙しい社会人や学生の方でも無理なく通えるコースとなっている。
◆10月から始まる新学期に向けて、説明会を順次開催!
オンラインでの参加も可能なため、忙しい方や遠方にお住いの方も気軽に参加可能。https://www.ncws.co.jp/flow/guidance/entry/
▼奥村裕則さん宣伝プロデュース担当作品

映画『九龍ジェネリックロマンス』8月29日(金)より全国公開
懐かしさが詰まった街・九龍を舞台に繰り広げられるミステリー・ラブロマンス。
https://kowloongr.jp/movie/
インタビュー すべてのバックナンバーはこちらからご覧いただけます!




COMMENT
コメントをするにはログインが必要です。不明なエラーが発生しました